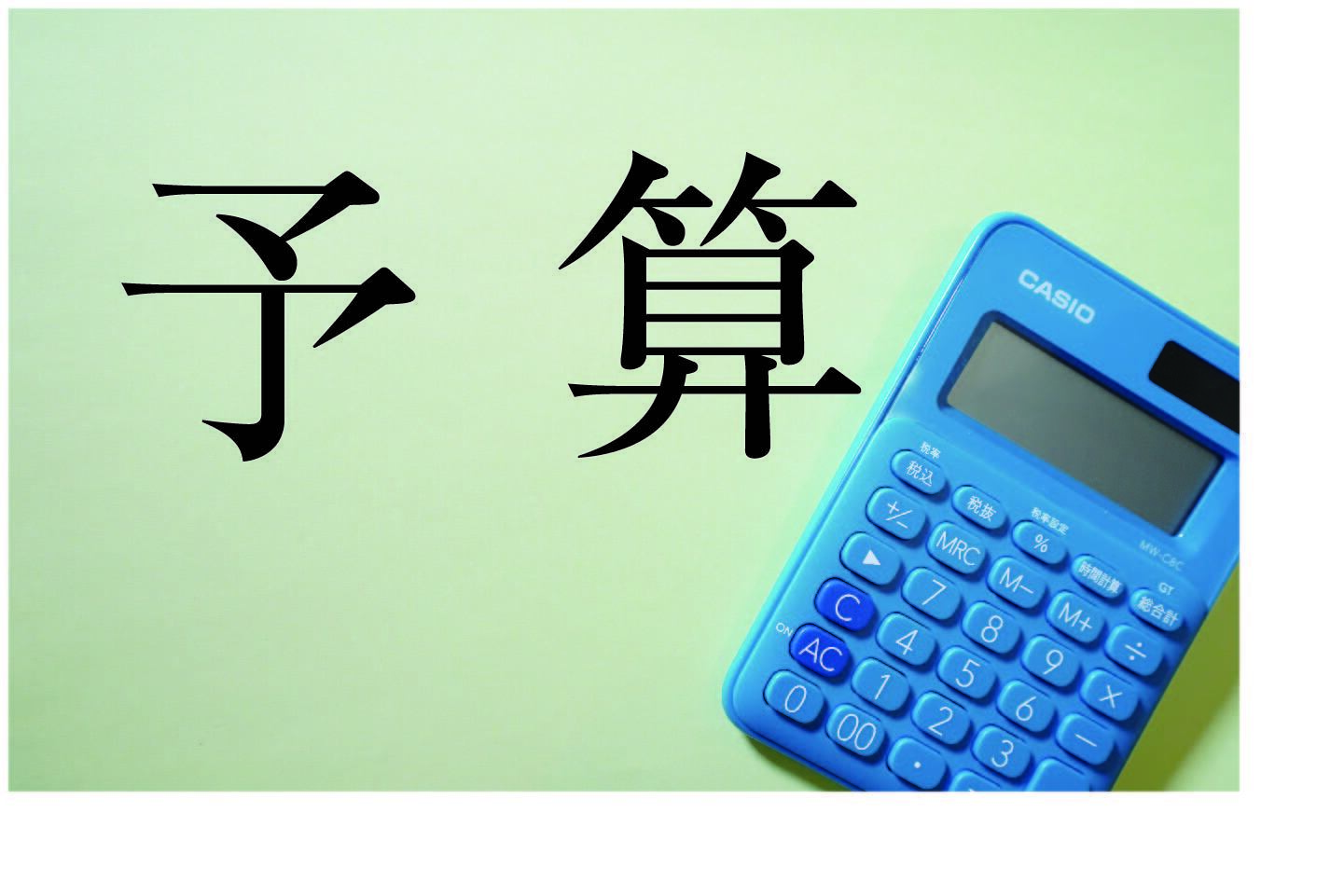林道施設の「老朽化・長寿命化対策」など“強靭化”を推進
前編に引き続き、林野庁の来年度(2023年度)当初予算と今年度(2022年度)補正予算のポイントを解説していこう。
まず、前回取り上げた治山事業とともに林野公共事業の双璧をなす森林整備事業について。昨年(2022年)8月末の予算要求時に打ち出していたのは、①間伐の着実な実施、②主伐後の再造林、③幹線となる林道の開設・改良等の推進──の3つであり、とくに③に重点を置いていた。その“答え”として、2023年度当初予算に盛り込んだのが「林道施設の老朽化・長寿命化対策」。メンテナンスの緊急度が高い林道施設(橋梁、トンネル等)を対象にした老朽化対策を加速化するため、既存事業を見直して補助メニューを拡充する。
「森林作業道の改良・復旧対策」を実施することも、2022年度補正予算で措置された。これまでは間伐等の森林施業と一体的に改良・復旧を行う場合に補助をしていたが、新たに単体で実施する改良・復旧も支援対象にする。
また、林業適地における路網整備をテコ入れするため、助成対象となる地域要件に、市町村森林整備計画で定める「効率的施業区域」を加えて支援範囲を広げることにした。加えて、大雨等による被害拡大を未然に防止する「機能回復」を補助メニューに新設する。
一連の見直しが目指していることを一言で表現すると、“強靭化”の推進となる。伐出量が増え、木材の大径木化も進んで運材車が大型化しているほか、想定外の大雨など災害時への備えも喫緊の課題となっている。よりタフな道を整備していくことが求められているのだ。
新規の「循環成長対策」に72億円、「デジタル・イノベーション対策」は6億円
次に、非公共事業の仕上がりをみていこう。
前編で解説したように、非公共事業の2023年度当初予算は対前年度比7.2%増の1,077億円に伸びたが、増額をもたらしたのは、義務的経費である「国有林野事業の債務返済経費」の増加だった。新規事業などに使える政策的経費は前年度より約14億円減っており、2022年度補正予算(227億円)を合わせた全体の規模でも前年度から約9億円縮小した。
もともと非公共事業は、潤沢とはいえない財源をやりくりして各種の施策・事業を行っているのだが、さらに台所事情が苦しくなる中でメリハリをつけざるを得ないという状況になっているわけだ。
そうした背景を踏まえた上で、非公共事業の目玉要求がどうなったかをみていこう。
まず、既存の「林業・木材産業成長産業化促進対策」を衣替えして118億円を新規要求していた「林業・木材産業循環成長対策」は、72億円が認められて実施する運びとなった。ネーミングを「循環」に切り替えたのは、新たに「再造林低コスト化促進対策」を柱に据えたから。一貫作業や低密度植栽等による低コスト造林をさらに進めるため、エリートツリーやコンテナ苗等の増産に向けた施設整備などについても助成する。併せて、木材加工流通施設の整備や路網の開設・改良、高性能林業機械の導入、木造公共建築物の整備などについても従来どおり支援していく方針。なんでもできる補助事業に再造林関係のメニューが加わったかたちとなっている。
もう1つの新規目玉である「林業デジタル・イノベーション総合対策」は、32億円を要求していたのに対し、認められたのは6億円にとどまった。とくに、目玉中の目玉として10億円を新規要求していた「デジタル林業戦略拠点構築推進事業」の予算額は1億2,000万円と大幅に減額査定された。このため、実施地域を当初予定の10か所から3か所程度に絞り込むという。全体の事業規模はスケールダウンを余儀なくされたが、林業イノベーションハブ構築事業などの補助メニューは一通りのラインナップが揃っており、限られた財源を有効活用して実績を上げていくことになる。
継続事業は横這い・減額だが、中身を見直して新規を捻り出す
このほかの主要事業についても、ざっと要点をさらっておこう。川下関係の「建築用木材供給・利用強化対策」は16億円の要求をしていたが、ついた予算は12億円。前年度は13億円だったので、実質的にはほぼ横這いの予算規模となった。同対策では、都市の木造化等を促進するため、JAS製品の供給力強化やCLTの寸法標準化などに取り組む。サプライチェーンマネジメントを形成する顔の見える木材安定供給体制の構築では、森林経営の持続性に配慮することを明確にして、川上~川下の連携強化を目指すという。
「木材需要の創出・輸出力強化対策」は、前年度と同額の4億円を確保した。非住宅建築物等での木材利用を促進するため、工務店等の支援体制の構築にも力を入れていく方針だ。木質バイオマス利用に関わる「『地域内エコシステム』展開支援事業」では、新たに情報提供や交流促進の機能を持つプラットフォーム(リビングラボ)の構築を支援する。「『クリーンウッド』実施支援事業」も、法改正を睨みながら進めることにしている。
6億円を要求していた「『新しい林業』に向けた林業経営育成対策」には3億円の予算がつき、前年度と同額の規模で継続することになった。これまでに12件のモデル的取り組みを選定しているが、予算の増額はならなかったので、これ以上の追加選定はせずに、事業内容を充実させていくという。なお、同対策とともに経営課が担当している「森林・林業担い手育成総合対策」は、前年度より1億円減の47億円で継続する。
山村・緑化関連の要求事項は厳しく査定された。関係人口の拡大などを目指す「森林・山村地域振興対策」は、前年度の14億円から11億円へ3億円の減額。また、「カーボンニュートラル実現に向けた国民運動展開対策」は、前年度の半額にあたる1億円で実施することになった。
ただ減額の中でも、森林由来J-クレジットの活用促進や自治体支援の専用サイトを構築する「山の炭素吸収応援プロジェクト」を2,900万円で新たに立ち上げ、芽出しをすることにしている。予算増は見込めない中で、知恵を絞って何とか新規事業を捻り出した。何事も順風満帆とはいかないものだ。
(2023年1月10~13日取材)

詠み人知らず
どこの誰かは知らないけれど…聞けないことまで聞いてくる。一体あんたら何者か? いいえ、名乗るほどの者じゃあございません。どうか探さないでおくんなさい。