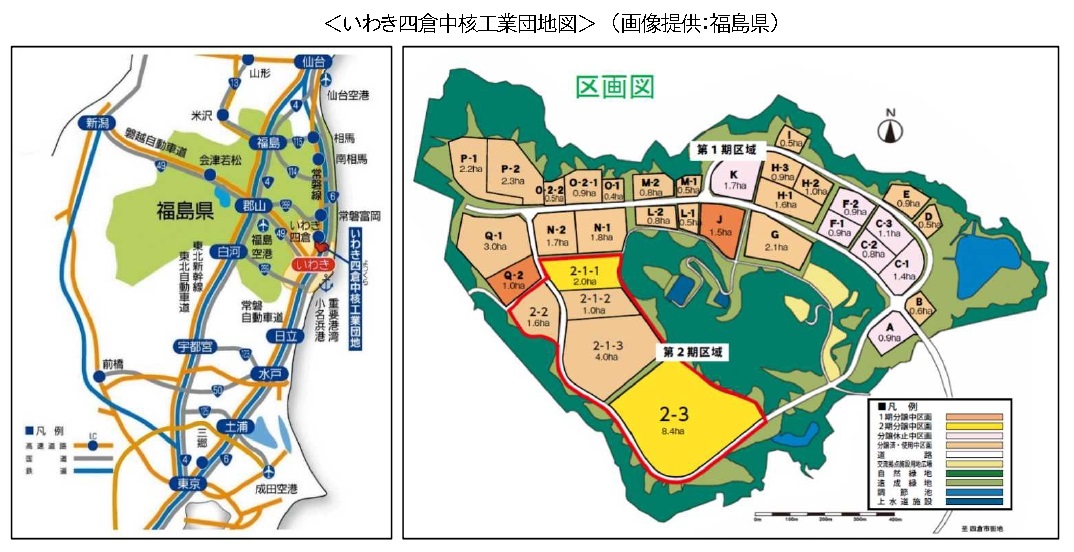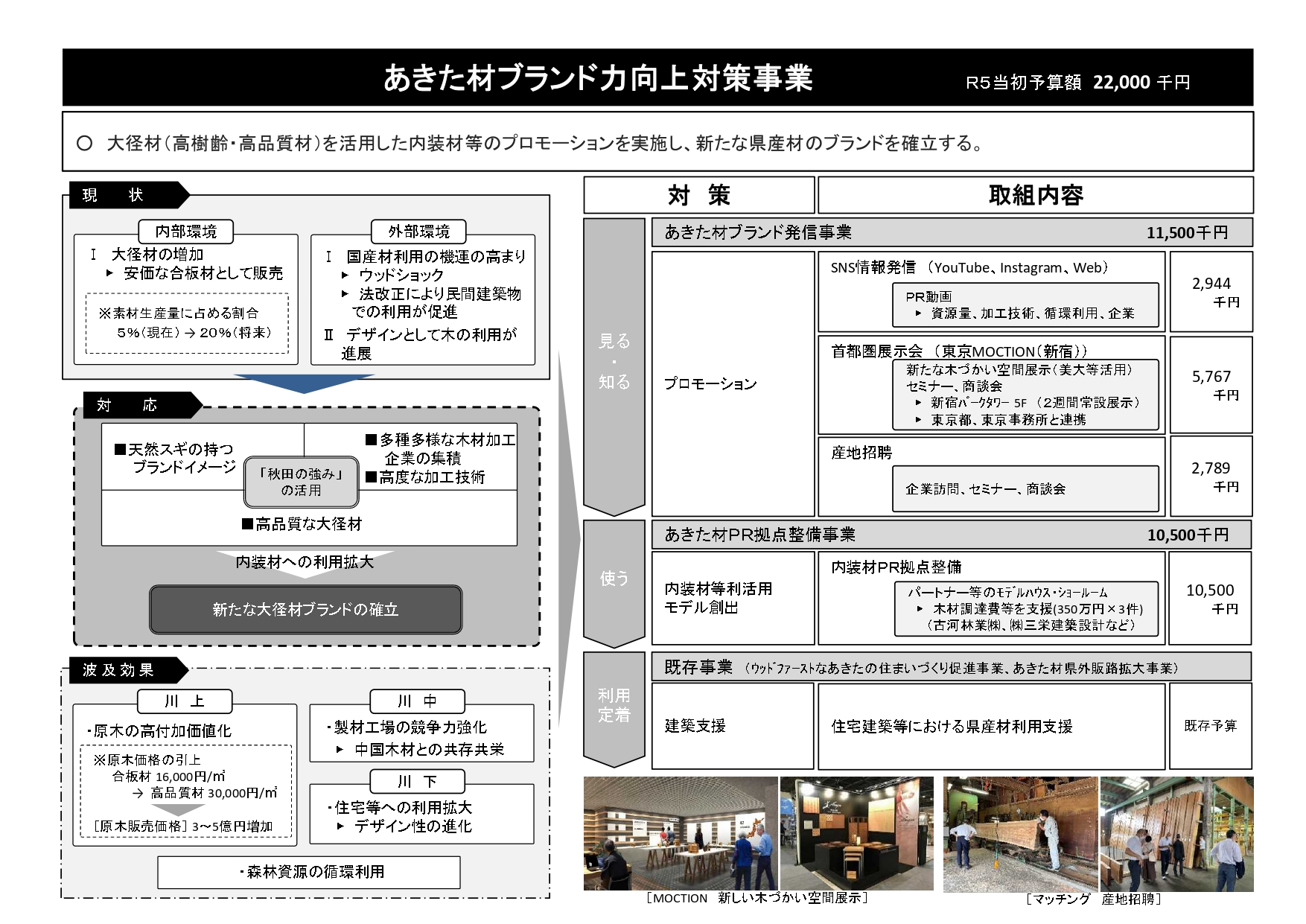目次
約1,000m3の粗挽き製品を常時保管し様々な注文に応える
「丸太からできるだけ大きく挽いて保管しているんですよ。ウチはほとんど注文材ですから。様々なニーズに応えるためです」──こう話すのは寺島木材の寺島信弘社長。
同社は、国産大径木をメインに年間約1,200m3の原木を取り扱っている。仙台市内にバンドソーなどを有する加工拠点を2か所持ち、土場や倉庫を含めた総敷地面積は約7,000坪に及ぶ。
土場に積まれている原木は、最長8m、直径30cm以上のスギ、ヒノキ、アカマツ、カラマツ、モミ、ケヤキ、クリなど。東北や北海道、関東などから調達したものだ。
倉庫には、これらの原木を粗挽きした製品がストックされ、天然乾燥が施されている。保管量は、常時1,000m3ほどになる。
注文が入ると、粗挽きした製品を加工し、最終製品に仕上げて納める。
同社のように長尺で大きなサイズの製品に関するニーズにフレキシブルに応えられる製材所は他にない。素材生産業者は大径の原木が出材されれば同社に持ち込み、工務店や木材業者などは高級材に関わる注文や相談を同社に問い合わせることが当たり前の風景になっている。
一番のウリはケヤキ、飲食店のカウンターなど新用途を提案
様々な高級材を扱う寺島木材の中で、一番のウリとなっているのがケヤキだ。倉庫には長さ6m、幅60cmを超える皮付きの角材や板が豊富に保管されている。ケヤキは、伐採してから使えるようになるまでに約10年間は天然乾燥する必要がある。乾燥をスムーズに進めるために、敢えて皮付きでストックしている。
これまでケヤキは、社寺仏閣用材や個人邸宅の化粧柱などに使われてきた。だが、こうした需要は先絞りの傾向にある。そこで寺島社長は、飲食店のカウンターやテーブル用としてケヤキの利用を広げようとしている。

仙台市の繁華街である国分町に無節のケヤキをL字カウンターに使ったバーが9月中にオープンする予定だ。納めたのは、もちろん同社。カウンターの長さは4ⅿ、幅は50cmとワイドなサイズになる。同社は、別の店舗に長さ8m、幅80cmのケヤキカウンターを納品したこともある。
コロナ禍で飲食業界は苦境に喘いでいたが、ようやく復調の兆しが出てきている。寺島社長は、「いずれは国分町のカウンターをすべてケヤキにしていきたい」と意気込んでいる。
年約600m3の土木材生産、アカマツからスギへの転換も視野
高級材と並ぶ寺島木材のもう1つの柱が土木材だ。現在は、年間約600m3の土木材を生産している。

主にアカマツなどの小径木を丸棒の杭材に加工しているほか、矢板もコンスタントに生産。大径材からは特殊なサイズの矢板をつくるなど、ここでも様々な注文に応えている。
地元の公共工事では、使用樹種にアカマツが指定されている。だが、アカマツは住宅用材としても人気があり、価格が高騰して取り合いになっている状況だ。寺島社長は、「マツ枯れが進んでおり、アカマツの供給量には天井が見え始めている」と危機感を隠さない。今後に向けては、「県産スギに転換していく必要がある。強度が足りないのならば厚みを出して対応していくしかない」と話している。
木工教室を開催して周囲を巻き込み、“木を見る目”を養う
寺島木材の社員は7名。年間の売上高は約1億5,000万円。同社のある仙台市泉区には、かつて12の製材所があったが、今では同社だけになった。
寺島社長は、「豪雨時などに整備が行き届いてない森林から丸太が流れ出てくることもある。地元の森林資源を伐って使うことが益々重要になっている」と強調し、「子供たちや若い世代に木の良さを伝えて、周囲を巻き込んでいくことが必要だ」と続けた。

寺島社長は宮城県木材同友会(同市)の一員で、休日には同友会の会員とともに、親子向けの木工教室を開催している。「子供たちが木に触れて楽しそうしていると、大人も参加するようになる」と話し、「『パートタイムで働かせてください』と頼まれることもある」という。実際に、希望者には配送や軽作業の手伝いをしてもらうこともあるが、そこには「多くの人に木の良さを知ってもらい、“木を見る目”を養ってほしい」という願いが込められている。

同社の製材加工業務で最も重要な「木取り」は、27歳の職人2名が担っている。「先代から“木を見る目”を継承できてよかった」と話す寺島社長は、「これからも地域に密着した製材所を目指していく」と決意を新たにしている。
(2022年7月7日取材)
(トップ画像=倉庫に保管されている粗挽きした製品)
『林政ニュース』編集部
1994年の創刊から31年目に突入! 皆様の手となり足となり、最新の耳寄り情報をお届けしてまいります。