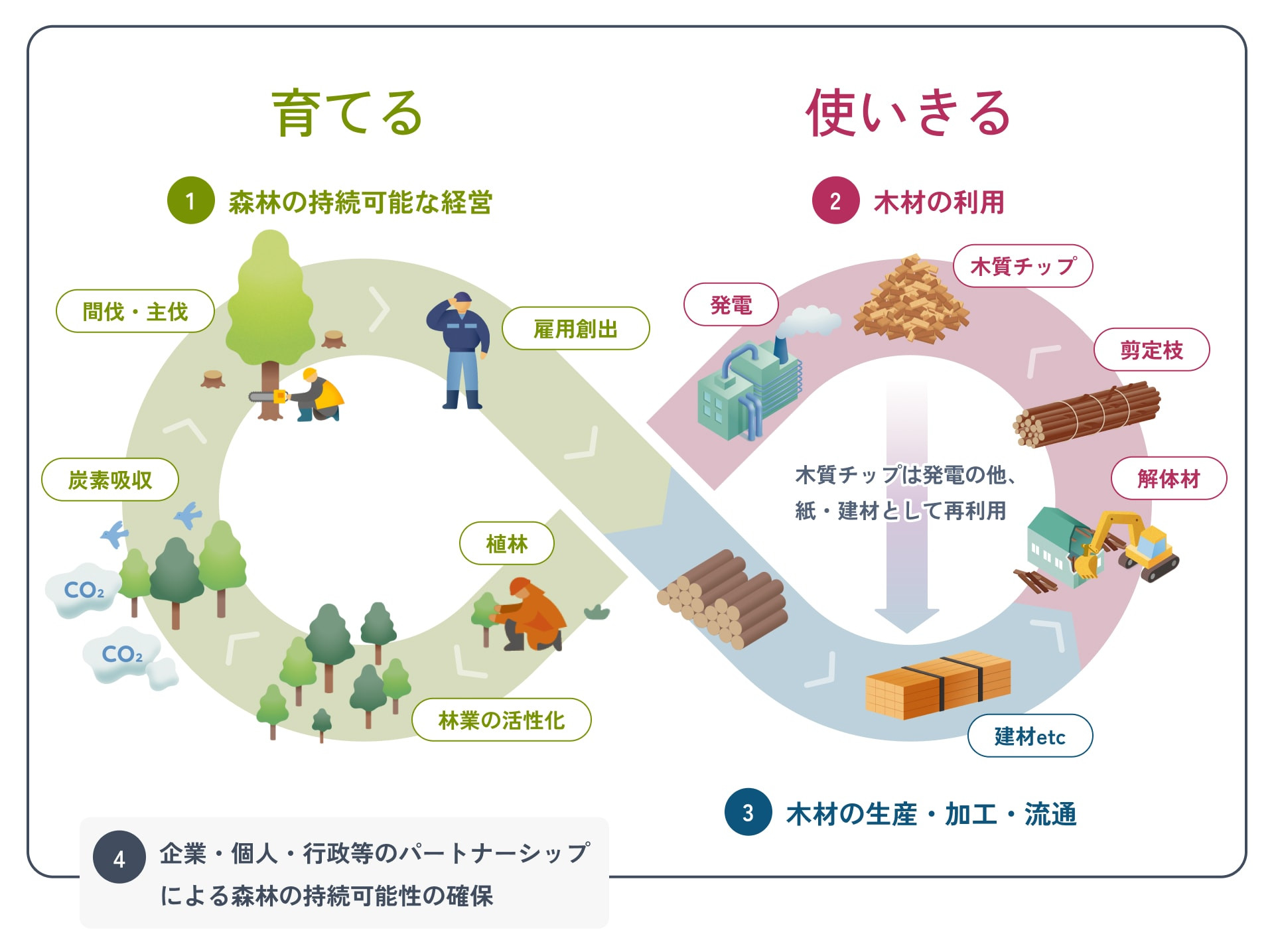目の前のシカ害を放置することはできない、年約800頭を捕獲
「シカによる樹皮剥ぎは、育ててきた木、とくに最も値打ちのある元玉の価値を一気に下げる。林業会社を経営していて、目の前のシカ害を放置しておくことは到底できなかった」──中津造林の衛藤正明社長はこう話し、「自分達でシカを獲るしかないと考えた」と捕獲班を立ち上げた理由を語る。衛藤社長は、自ら猟銃を扱う猟師でもある。

捕獲班を持つ同社は、7年ほど前から森林管理署や県、市町村などからシカの捕獲事業を請け負っており、年間の捕獲数は約800頭に達している。猟期となる11月から3月の間は、ほぼ毎日、捕獲班のメンバーも山に入り、ワナや猟銃を使った狩猟を行っている。
捕獲班の活動エリアは大分県内に限らない。他県にも足を運び、山奥に行くこともあれば、人里に近い場所に出向くこともある。衛藤社長は、「シカ害対策で悩んでいる自治体などからの依頼が多い。他県でも猟師が少ないような地域に足を運んでいる」と言う。
同社が継続的にシカを捕獲している効果は着実に表われてきている。夜中にシカが出没していた地域の住民からは、「シカが近くに出てこなくなって安心して眠れるようになった」という声も届いている。なお、同社は、鳥獣保護管理法に基づく認定鳥獣捕獲等事業者となっている。
猟友会に思いを伝え「捕獲班」編成、次代を担う猟師を育てる
中津造林は、1980年に造林業者として創業し、素材生産事業も手がけるようになった。現在は12台の林業機械を保有し、間伐を中心に年間1万m3程度を伐出しているほか、植林や下刈り、保育間伐を年間約50ha行っており、8名の正社員が従事している。
同社の捕獲班には22名が在籍しており、臨時従業員という位置づけになっている。メンバーの大半は兼業農家で、農繁期以外は捕獲班の一員になり、捕獲事業に従事している。
捕獲班を編成する上で衛藤社長が最も意を注いだのは、地元の猟友会と意思疎通を図り、連携体制をとることだった。捕獲班のメンバーは、基本的に猟友会の会員となっており、衛藤社長も猟友会に所属している。
「捕獲班を立ち上げる時には、猟友会のメンバーにできる限り思いを伝えるようにした。その結果、全面的な協力を得ることができた」と衛藤社長は振り返る。同社の捕獲事業の責任者は、宇佐市役所で鳥獣害対策の担当をしていた。このキャリアも、猟友会との円滑なパイプづくりに役立っている。
林業会社として捕獲班を組織した同社が直面している課題は、次代を担える猟師の確保と育成だ。全国的にも猟師の高齢化が問題になっている。
同社では、狩猟免許の取得・更新や安全講習などに必要な経費を負担するなど人材育成に向けた支援策を講じている。衛藤社長は、「いきなり猟銃を扱うのは難しいかもしれないが、ワナであれば取り組みやすい。誰でも猟師になれる可能性がある」と期待を込めている。
ジビエ加工施設も運営し、山からもたらされる資源を最大活用
中津造林は、4年前にジビエ加工施設をつくった。捕獲班が行っている捕獲事業と並行して、地元から持ち込まれるシカやイノシシを受け入れ、食肉処理などを行っている。加工したシカ肉などは近隣の道の駅などで販売しており、一定の手数料を差し引いた売り上げは関係者の収入になっている。

「加工施設があることで猟師の方々とより『密』なコミュニケーションがとれるようになった」と話すのは、専務取締役の衛藤亀鶴氏。亀鶴専務は正明社長の子息で、経営の一翼を担っている。

同社は、「大分ジビエ振興協議会」の一員として、シカ肉などの普及に取り組んでいる。亀鶴専務は、「飼料高騰の影響で豚肉や鶏肉などの価格が上がっている。いずれはシカ肉を食べることが当たり前になるかもしれない」と言い、今後の展開についてこう語った。「シカ肉の処理はスピードが大事であり、地域に根差した林業会社でなければできないことがある。木もシカも山からもたらされる貴重な資源であり、最大限に有効活用していきたい」。
(トップ画像=販売用にラッピングされたシカ肉)
『林政ニュース』編集部
1994年の創刊から31年目に突入! 皆様の手となり足となり、最新の耳寄り情報をお届けしてまいります。