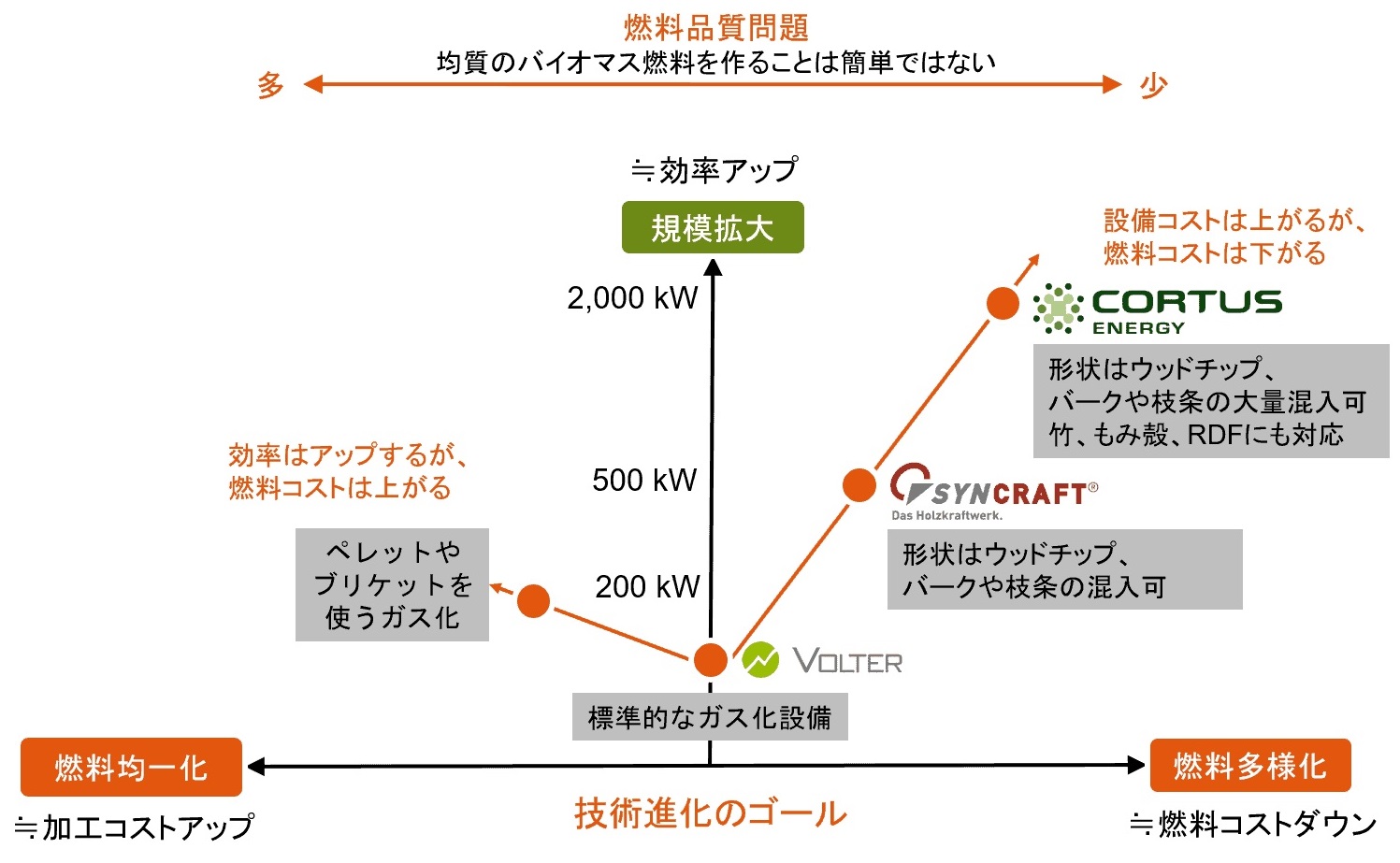目次
日本のバイオマス事業は発電優先、熱利用のインフラが不足
ヨーロッパの中山間地域などでは、それぞれの資源事情に合わせた熱電併給事業が活発に行われていると聞いている。なぜ、日本では同様の取り組みが広がらないのか。
弊社が取り扱っているガス化設備を開発しているフィンランドやオーストリアでは、電気とともに熱もきちんと使っていくというコンセプトがはっきりしていて、地域熱供給システムなどの社会インフラが整備されている。これに対して、日本の場合は、常に発電が優先されている。極端に言うと、木質バイオマス発電所を建設して電線につなげば、あとは売電価格が保証されているので事業が成り立つという仕組みになっている。
木質バイオマスの利用を発電から考えるか、それとも熱供給から考えるか、入り口の部分で違いが大きいわけか。
電線で電気を送るシステムは本当に効率がいい。長距離でも問題なく電気を運ぶことができる。しかし、熱の場合は、長距離輸送が難しい。発電所から配管をして施設や住宅などに温水を届けようとしても、その範囲には自ずから限度が出てくる。この違いをよく踏まえる必要がある。
フィンランドやオーストリアは、まちづくり自体がコンパクトになっており、小規模分散型で連携しやすいように設計されている。したがって、熱供給事業も展開しやすい。日本では、まず身の丈にあった規模で熱利用から始めていくべきだろう。
その身の丈にあった規模で熱利用を行っているモデル的な事例はないか。
弊社の渋川バイオマス研究所で行っていることは、1つの参考になるかもしれない。
廃校を再利用してイチゴの栽培も行う渋川バイオマス研究所
沼社長が言及したフォレストエナジーの渋川バイオマス研究所は、群馬県の渋川市にある。2014年3月末で廃校になった上白井小学校の校舎と敷地を再利用し、同社の取り扱うガス化設備「Volter 40」を導入して熱電併給事業を行うとともに、(株)NTTファシリティーズ(東京都港区)と連携して研究開発事業も進めている。校庭にはイチゴハウスがあり、ここでガス化発電に伴って生み出される熱を利用しながらイチゴの栽培を行っている。また、副産物として出てくる炭をJ-クレジット制度などで認められた「バイオ炭」として温暖化対策に活用することなどにも取り組んでいる。
昨年(2022年)12月8日には、関東森林管理局やぐんまフォレスター連絡会が主催して同研究所の見学会が行われ、約100名が参加するなど、地域に開かれた“熱電併給の学びの場”にもなっている。
廃校を木質バイオマス関連の研究所として“復活”させ、電気だけでなく熱をイチゴの栽培に利用するとはユニークだ。熱電併給の規模はどれくらいになっているのか。
電気は約40kWで一般家庭約60世帯分の消費量に相当する。熱は約100kWでイチゴを栽培しているビニールハウスの大きさは約100m2になっている。
林業関係者も見学に訪れているようだが、外に開かれた運営をしている狙いは何か。

熱電併給などの事業をできるだけ身近に感じてもらいたいからだ。そのために、見学会の開催なども1つのコミュニケーションの手段と位置づけて実施している。熱電併給を広げていくためには、事業に参入する際のハードルをできるだけ下げていく必要がある。このくらいのコンパクトな規模でもできるということを多くの方々に知ってもらいたい。
事業参入のハードルを下げて、顔の見える距離感で連携する
熱電併給を普及していくために、事業に参入するハードルを下げていくというのは重要な指摘だ。
例えば、島根県津和野町の津和野フォレストエナジーは、電気が480kW、熱が1,200kWというコンパクトな規模にして運営している。熱電併給システムを安定的に稼働させるためには、品質の確保された燃料チップを調達し続けなければならないし、そのための体制づくりや人材の確保・育成など、やるべきことがたくさんある。山積している課題を1つ1つ解決していくためには、様々な関係者が顔の見える距離感で取り組めるようにしておくことが重要になる。
津和野フォレストエナジーの場合は、その距離感がうまく保たれているのか。
地元の自治体が中心となり、関係者を巻き込んでできることから実践している。燃料材の集荷にあたって運賃補助を出したり、人材の確保・育成では地域おこし協力隊の仕組みを活用するなど、施策的な支援も行いながら、事業参入のハードルを下げるための工夫を重ねている。最も重要なことは、発電所をつくってから燃料材の集荷などに追われるのではなく、長期間にわたって山から木を継続的に出せる仕組みをつくり上げていくことだ。
燃料チップの品質に応じた価格差や輸送コストの削減が必要
山から木を長期・安定的に出す仕組みができれば、日本林業全体を底上げすることにつながる。大きなテーマだ。
日本林業全体を活性化するためには、やはり山や木の価値をもっと高めていくことが必要だろう。木質バイオマス発電や熱電併給事業で、C・D材や林地残材が利用され、これまで使い道がなかったものに売り先ができたことは前進といえるが、さらに価値を高めていく必要がある。例えば、燃料チップの品質によって価格差をつけることも考えられる。
チップの品質とは、サイズ(大きさ)や含水率(水分量)などの違いをいうのか。
そうだ。とくに、水分を多く含んだ生のチップと含水率を落としたチップとでは燃焼効率などが大きく異なってくる。含水率の低いチップは燃焼効率が高いが、乾燥コストがかかる。ヨーロッパでは、こうした点を勘案してチップの規格を整備しており、いわゆるレギュラーものやプレミアムのチップなどを選べるようになっている。ところが、日本では、このくらいのサイズで、このくらいの含水率のチップがこれだけ欲しいと言っても、どこで入手できるのかがわからないのが現状だ。
一口に燃料用のチップと括ってしまうのではなく、もっと価値を引き出す仕組みがつくれるということか。
チップの価値を高めるためには、輸送コストを削減することも欠かせない。発電所がチップを購入する価格はだいたい決まっているし、山側の再造林や育林、伐出などの費用もきちんと確保しなければならない。そうなると、利益率を高めるには、輸送コストの削減が必要になる。この点でも、燃料材の集荷圏が狭い小規模な熱電併給システムには、コストダウンを図りやすい優位性がある。今後も、大規模な発電所にはないメリットを活かしながら、地産地消型の木質バイオマス発電と熱電併給事業に取り組んでいきたい。
(2023年1月30日取材)
(トップ画像=渋川バイオマス研究所(手前がイチゴハウス))

遠藤日雄(えんどう・くさお)
NPO法人活木活木(いきいき)森ネットワーク理事長 1949(昭和24)年7月4日、北海道函館市生まれ。 九州大学大学院農学研究科博士課程修了。農学博士(九州大学)。専門は森林政策学。 農林水産省森林総合研究所東北支所・経営研究室長、同森林総合研究所(筑波研究学園都市)経営組織研究室長、(独)森林総合研究所・林業経営/政策研究領域チーム長、鹿児島大学教授を経て現在に至る。 2006年3月から隔週刊『林政ニュース』(日本林業調査会(J-FIC)発行)で「遠藤日雄のルポ&対論」を一度も休まず連載中。 『「第3次ウッドショック」は何をもたらしたのか』(全国林業改良普及協会発行)、『木づかい新時代』(日本林業調査会(J-FIC)発行)など著書多数。