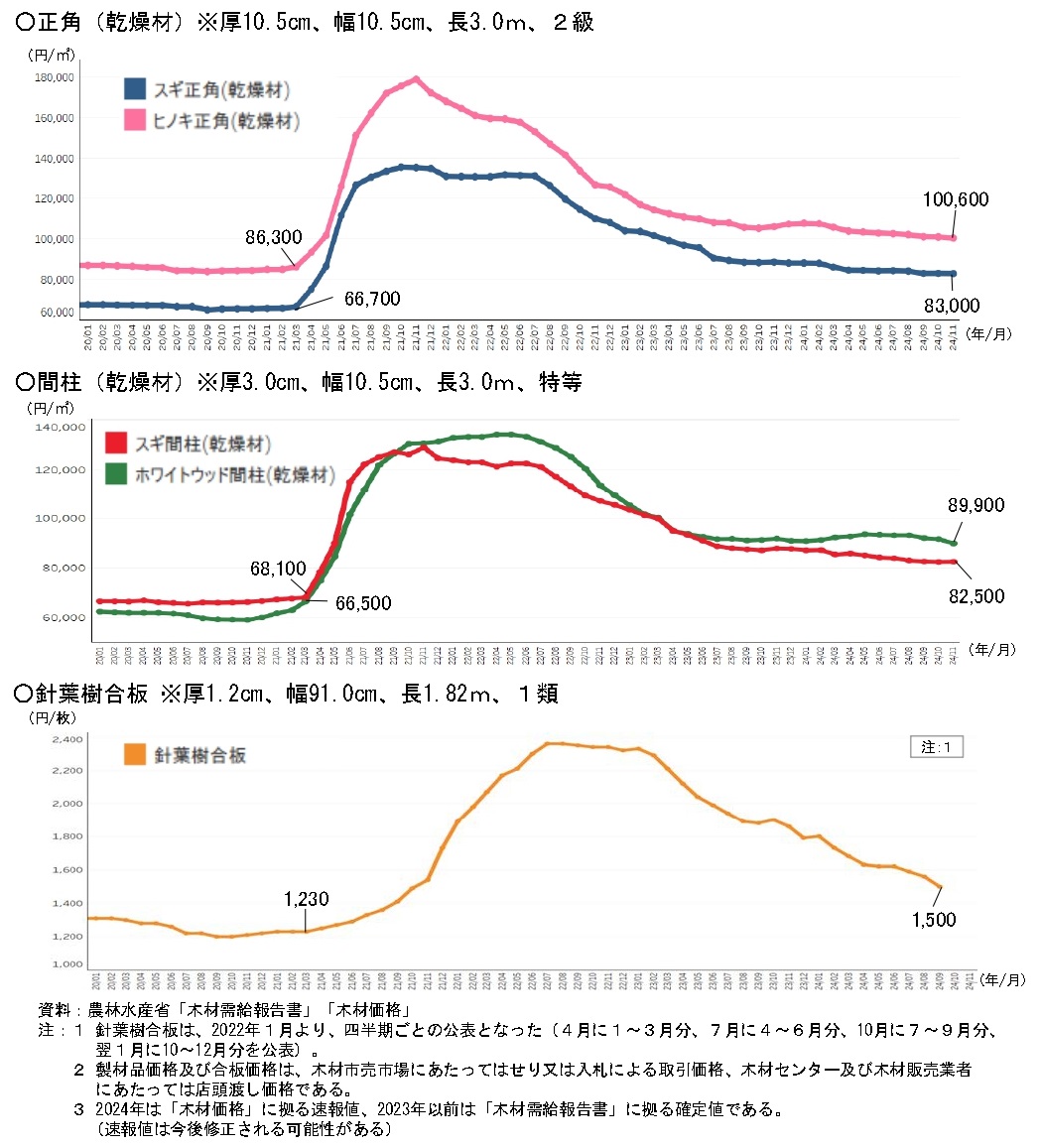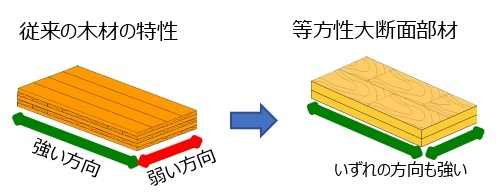B材丸太を効率よく低コストで届けるため伐採現場で仕分け
石巻地区森林組合の地元・石巻市には、セイホク(株)、石巻合板工業(株)、西北プライウッド(株)など錚々たる合板メーカーが工場を構えている。同組合は、この立地条件の中で、スギを主体とした合板用丸太を安定的に供給し続けている。 同組合の大内伸之組合長は、宮城県森林組合連合会の会長も兼務している。遠藤理事長とは、大内組合長が同組合参事の時代からの旧知の仲だ。
森林組合の丸太供給といえば系統共販事業が中心になる。その中で、石巻地区森林組合はいち早く合板メーカーへの丸太供給に挑んだわけだが、当時の状況はどうだったのか。

系統共販事業で扱う丸太は、A材とC材が中心だ。そこに突然、合板用のB材を供給して欲しいという要請が来たので、正直に言って戸惑いを隠せなかった。
それまでB材というジャンルがなかったのだから当然だ。
B材の供給は当組合にとって全く新しい取り組みであり、単独でやろうとしても対応が難しい。合板メーカーからは大量かつ安定供給が条件と言われ、宮城県森連や民間の素材生産業者に協力して欲しいと打診した。
反応はどうだったのか。
やはりB材を扱うことには躊躇(ためら)いがみられた。そもそもB材をどのように扱ったらいいのかわからないというのが実情だった。B材はA材に比べて単価が安いとみられ、共販(市売)にかけるとコスト高になる。
この問題を解決する道筋を提示しなければ、民間の素材生産業者の協力は得られないと考えた。
解決の道筋はどうやって見出したのか。
単価の安いB材丸太をいかに効率よく、低コストで合板工場まで運ぶかを何度も検討した結果、中間土場は設けずに、伐採現場でA材・B材・C材に仕分けし、B材を合板工場へ直納する供給ルートを考えた。この供給ルートを定着させるため、伐採現場での仕分けは綿密に行うようにした。すると、民間の素材生産業者も、共販所(市売)を通さない新たな供給ルートについて理解を示すようになり、だんだんと仲間が広がっていった。その結果、合板工場へ納入する丸太の量も年々増えていった。
合板用丸太生産量が約30万m3に、積極的な買取林産が奏功
宮城県林業振興課が発行している「みやぎの森林・林業」の用途別素材(丸太)生産量をみると、2005(平成17)年に初めて合板用丸太の生産量が記述されている。以後、着実に増え続け、2020(令和2)年の全素材生産量(57万6,000m3)に占める合板用丸太の割合は44.4%、25万6,000m3に達している。
2021(令和3)年の速報値では、合板用丸太の生産量は29万2,000m3に伸びている。このうち当組合が占めるシェアは19%でほぼ2割という水準だ。
単独の森林組合が先導するかたちで、ここまで生産量を増やせたのはなぜか。
従来からの受託生産に甘んじているのではなく、森林組合が立木を買い取って伐出・販売をする買取林産を積極的に増やしてきたことが大きい。

石巻地区森林組合と連携関係(友好組合)にある宮崎県の南那珂森林組合も積極的な買取林産事業を展開していることで知られている。
「令和元年度森林組合一斉調査結果」によると、全国の森林組合数は613組合で、合併などによって年々組合数は減っている。その中で、石巻地区森林組合や南那珂森林組合のように積極的な事業展開をしている組合とそうでない組合との格差は益々広がっているといえる。
スギを中心にコンスタントな納入を目指す、再造林にも注力
ところで、合板メーカー各社への丸太納入は、具体的にどのように行っているのか。
納入している丸太の樹種はスギ、アカマツ、カラマツだ。中心はスギで、径級は末口16㎝から元口50㎝までで、最大直径50㎝以内としている。トラックへの積載本数は14㎝が3%、16㎝が10%までという条件になっており、例えば200本を積載した場合は、14㎝が6本、16㎝が20本という計算になる。
合板メーカーからの注文はどのように受け付けているのか。
先方からは月ごとに注文が来る。樹種別に、2m、4mの丸太が何m3欲しいというような具合だ。
納入価格の交渉はどうやっているのか。
当組合が窓口になって、合板供給会議の4団体とともに合板メーカー各社と行っている。
さきほど注文書を見せてもらったが、「(特定の日に)集中しないで日々平均的な納入をお願いいたします」と記してあった。これが安定供給の基本なのではないか。
そのとおりだ。そのためには、買取林産を含めた積極的な林産事業によって丸太の供給力を高めることが不可欠になる。
買取林産事業を推進していくと伐採跡地の再造林を確実に実施していくことが大きな課題になってくる。
そのために当組合などが呼びかけて2008(平成20)年に「みやぎ森林づくり支援センター」を創設し、県内の個人の再造林者に対し、2021年度は56ha分の支援を行っている。なお、当組合の同年度の事業実績は、植栽が22haだった。
引き続き、同センターと連携しながら当組合が目指す「循環型林業(一貫作業による低コスト再造林の推進)」を実践していきたい。
石巻地区森林組合は、全国に先駆けて合板用丸太の供給ルートを確立しただけでなく、再造林の支援など、常に一歩先を行く取り組みを行っている。大内組合長は宮城県森連の会長でもあり、今後も国産材業界全体を先導していただきたい。
時代の変化に対応しつつ、誠心誠意頑張るつもりだ。
(2023年4月10日取材)
(トップ画像=宮城県森連傘下の共販所に並ぶA材(製材用)丸太)
『林政ニュース』編集部
1994年の創刊から31年目に突入! 皆様の手となり足となり、最新の耳寄り情報をお届けしてまいります。