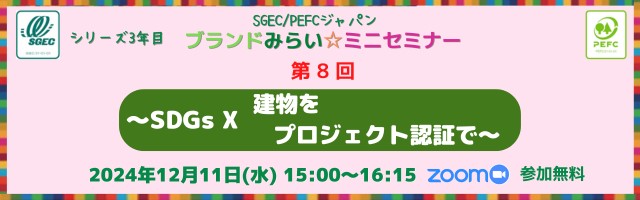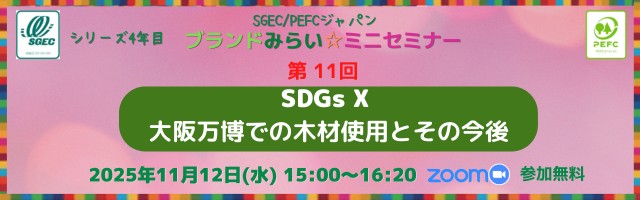48か国と連携、認証面積はロシア・ウクライナ戦争で減少し約2億8,800万ha
PEFCは、1999年に欧州11か国の森林認証制度を相互に認め合う組織として発足した。2003年に「PEFC森林認証相互承認プログラム」へと改称し、世界各国の認証制度と相互認証を行う国際認証組織として本格的な活動を開始した。
2022年末時点では48か国の制度と相互認証し、日本の緑の循環認証会議(SGEC)とは2016年6月に相互承認を取り交わしている*1。
認証林の面積は発足当初から右肩上がりで伸びてきたが、ロシアのウクライナ侵攻によりロシア・ベラルーシの認証を取り下げたため減少に転じ、2022年末時点の合計面積は約2億8,800万haとなっている。
国、所有者・企業レベルで異なる課題、日本の取り組みに期待
世界銀行によると、国際市場での木材需要は2050年までに4倍になると予測されている。バーガー氏は、「森林に大きなプレッシャーがかかることになる。持続可能な森林管理は必要不可欠であり、とくに28%しか認証されていない産業用丸太の認証率を引き上げていくことが重要だ」と強調した。
森林認証制度を広げていく際の課題は、国レベルと森林所有者・企業レベルでは異なる。国レベルでは、同制度の導入が可能な国はすで対応を終えており、今後普及していく国々は政府に期待できないか、もしくは経済的な困難が予想されている。バーガー氏は、「原則(持続可能な森林管理)を押さえた上で、制度を柔軟かつスピーディーに地域の事情にあった形にしていく必要がある」との考えを示した。一方、森林所有者・企業レベルでは、複数の所有者・企業が協力して認証をとるグループ認証によって取得のハードルを下げていくことが有効とした。
バーガー氏は、「普及にあたって最も大事なのは認証ラベルの認知度向上であり、日本は『チャンピオン企業』を認定するなど、アジア地域での森林認証の発展に貢献できる」と期待を寄せた。
偽装問題には罰則など厳しく対処、リソースを有効に活用する
同セミナーでは、バーガー氏の講演後、滑志田隆・日本林政ジャーナリストの会会長とのトークセッションや参加者との質疑応答が行われた。
その中では、認証を取り下げたロシア産の丸太・製品が中国を経由して認証材として流通しているのではないかとの指摘や、昨年(2022年)10月に発覚したベトナムの大手バイオマス燃料業者によるFSC認証偽装問題の影響を尋ねるものがあった、
これに対し、バーガー氏は、「PEFCはオランダ政府TPACなどから第3者評価を受け、信頼性と妥当性を得ている」と説明し、「もし偽装のような事態があれば、エビデンス(証拠)を取得し事態を究明し、認証の取り下げや罰則を課す。そして、再発防止のため認証基準を高く厳しくする」との対応方針を示した。
PEFCでは、認証審査に衛星リモートセンシングなどを活用し、審査コストの削減や測量精度の向上を図っている。バーガー氏は、「リスクが高いところは重点的に審査し、低いところは簡素化するなどリソースを有効に活用して認証制度を広げていきたい」と語った。
(2023年4月5日取材)
(トップ画像=PEFCのマイケル・バーガー・CEO兼事務局長)
『林政ニュース』編集部
1994年の創刊から31年目に突入! 皆様の手となり足となり、最新の耳寄り情報をお届けしてまいります。