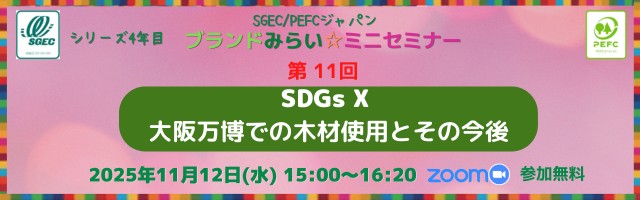杭丸太の炭素貯留効果を分析、地下水位以深の条件なら「永久」
建築物の基礎(下部構造)を固める地中利用木材、いわゆる杭丸太の歴史は極めて古い。例えばベネチアでは、16世紀末建造のリアルト橋をはじめとして、杭丸太が基礎に広く用いられ、長期間にわたって腐朽しないことが知られてきた。
第2次世界大戦後、杭丸太はコンクリート杭や鋼管杭に置き換わってきたが、2010年以降、軟弱地盤対策等として杭丸太を利用する新たな工法が開発され、再び注目されるようになってきた。
日本政府は、建築物等に用いられる木材(伐採木材製品:HWP)による炭素貯留量を、毎年、国連気候変動枠組条約事務局に報告している(温室効果ガスインベントリ報告)。しかし、杭丸太での利用については、炭素貯留効果の算定方法が確立されていないため、報告の対象となっていない。そこで、JIFPROでは、林野庁補助事業を活用し、森林総合研究所をはじめ関連団体や企業のご協力をいただいて、過去に施工された杭丸太を掘り出し、木材の容積密度などから炭素貯留効果を科学的に分析してきた。これまでに、施工後の経過年数が8年から100年にわたる7つの事例を調査し、①地下水位以深の条件では永久貯留と考えてよいこと、②長期間地下水位以浅にあった場合でも断面が欠損するような分解は認められず、質量減少半減期(質量が初期値の半分になるまでの期間)は短くみても約300年であること──がわかった。これらの結果に基づき、杭丸太の炭素貯留効果の算定方法を提案したところである。
シンポに約500名参加、「木地協」中心に賛同の輪を広げる
私共は、杭丸太を用いて認定を取得している建築・土木用4工法の打設量に関する調査も行った。近年は年間3万m3弱で推移しており、4工法の炭素固定効果は年間1万6,000~1万8,000CO2-ttと推計された。一方で、土木分野における杭丸太の使用量はここ5年ほど伸びていないという調査結果もあり、地球温暖化対策として杭丸太の利用拡大を図ることが大きな課題になっている。
そこで土木学会木材工学委員会とJIFPROは、1月20日に東京都内で「第1回木材地中利用シンポジウム」を開催したところ、オンラインを含めて約500名が参加し、関心の高さが窺えた。さらに、5月29日に開催予定の土木学会木材工学委員会主催の第15回木材利用シンポジウムでも地中木材利用について報告される。
これらを踏まえて、「地中の森が作る安心・安全社会」とのスローガンの下、一般社団法人日本木材地中活用推進協会(略称:木地協)を新たに設立される予定となっている。木地協では、木材地中利用による炭素貯蔵量の把握をはじめ、気候変動緩和・適応対策や安全・安心社会構築への貢献、さらに川上である健全な林業経営や森林資源の循環利用に寄与することを目指している。
空気中の二酸化炭素(CO2)を回収して地中深くに注入するCCSやCCUSと呼ばれる技術が注目されているが、杭丸太などの地中利用木材は、自然力を活用した低コストで、しかも軟弱地盤対策や森林資源の循環利用としても有効な一石二鳥、三鳥のCCUSと言え、その推進が大いに期待される。
(2025年3月21日受領)
(トップ画像=85年前に打設された橋脚基礎丸太の引き抜き。腐朽はみられない。(画像提供:福井県小浜土木事務所))

高原繁(たかはら・しげる)
2015年まで林野庁の技官として、国有林の管理や民有林行政(佐賀県庁)のほか、海外は在ケニア大使館やJICA専門家としてインドネシアで勤務。退職後、日本治山治水協会を経て、2020年にJIFPROに入り、開発途上国の森林保全や森林復旧のための植林事業、技術開発、林業や木材産業を通じた気候変動などのグローバルな課題への貢献に取り組んでいる。