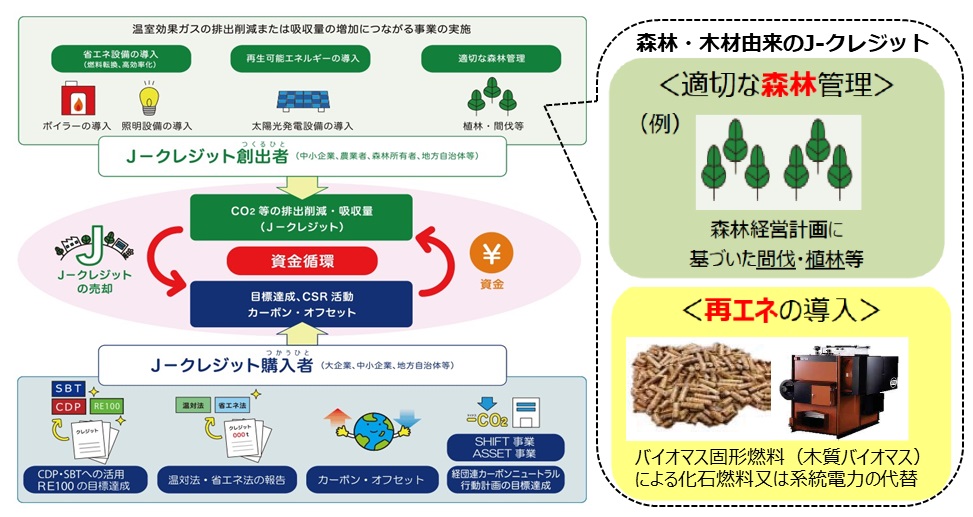「2050年ネットゼロ」に向けて新・地球温暖化対策計画を閣議決定へ
パリ協定の枠組みに沿って温暖化対策を進めている政府は、「2050年ネットゼロ」(カーボンニュートラル)を達成するため、CO2などの温室効果ガスを2013年度比で2035年度は60%、2040年度には73%削減する「野心的な目標」を新計画に盛り込むことにしている。
新計画は2月中に閣議決定する予定であり、森林整備や木材利用を通じたCO2の吸収・固定量への注目度がさらに高まりそうだ。
算定手法をモデル推定から実測に切り替えて高いハードルクリア
森林のCO2吸収量を3,800万tから7,200万tにほぼ倍増させる目標値の設定はかなり背伸びしたハードルに映るが、林野庁は、森林吸収量の算定方法を見直すことで達成できるとしている。
現在の算定方法は、森林簿や成長モデルを利用して、森林蓄積の増加量を推定し炭素量に換算している。この方法では、植栽木以外の自然に生えてきた侵入木は対象にならず、高齢級の人工林や天然林では蓄積推定に誤差が出やすいという難点がある。
そこで林野庁は、来年度(2025年度)から全国レベルの森林調査(NFI:National Forest Inventory)のデータを用いることにした。具体的には、1999年度から継続実施している「森林生態系多様性基礎調査」で得られたデータを活用する。同調査によって森林資源量に関する時系列データが蓄積されてきており、林野庁が設置した有識者検討会における議論と検証や、第三者機関による品質検査などを通じて統計的な信頼性が担保されたため、算定方法を切り替えることにした。
新しい算定方法では、林業目的以外の樹種も含めてすべての立木を対象に実測を行うので、森林の蓄積や成長量を高い精度で把握できるようになり、吸収量が増大することになる。諸外国もNFI関連データを使って森林吸収量を算定しており、国際標準に沿った見直しになる。
(2025年1月22日取材)
(トップ画像=森林簿・成長モデルとNFI(全国レベルの森林調査)による蓄積・成長量の推定差(イメージ))
『林政ニュース』編集部
1994年の創刊から31年目に突入! 皆様の手となり足となり、最新の耳寄り情報をお届けしてまいります。